
| 野 鳥 歳 時 記 |
−横田俊英 論説員、日本野鳥の会会員−
シジュウカラ→コマドリ→サンコウチョウ→キセキレイ→ウミネコ→
ホシガラス→カワガラス→コゲラ→カルガモ→アカハラ→
ゴジュウカラ→シロアジサシ→ホトトギス→カワセミ→
カワウ→
ヒバリ→ホオジロ→ヒヨドリ→コジュケイ→カワラヒワ
→キジバト→ウグイス→ツバメ→ウソ→キジ
|
|
||

|
月星日 日本の夏は サンコウチョウ 虚心
|
||
|
8月になると台風も20号近くになります。8月の後半にきた台風の後には秋のにおいがするものです。木々の濃い緑に疲れが見えるようになりますと、夏鳥の渡りが気にかかります。8月の終わり近いある日の朝、「月(つき)、星(ほし)、日(ひい)」の声が聞こえてきました。あれっ、と思いつつ10回ほど声を聞いて、間違いないサンコウチョウだ、と確信して嬉しくなりました。「月、星、日」は、人によっては「月、日、星、ホイホイ」と聞こえるようです。 |
||
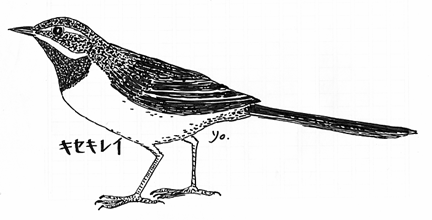
|
キセキレイ 岩魚と遊ぶ 夏河原 虚心
|
||
|
キセキレイは目立つ野鳥です。キセキレイと特定しなくてもセキレイの仲間の、ハクセキレイもセグロセキレイも人をあまり恐れないため、姿をしっかりと見ることができるから印象にのこるのです。セキレイの仲間は、長い尾を独特の調子で振り、波形に上下して飛びますし、体色の白と黒のコントラストがまことに鮮やかです。キセキレイの場合には腹部の黄色が鮮烈です。
啼き声はツツン、ツツンあるいはチチン、チチンと聞こえます。メスの体色はオスに比べて腹部の黄がうすく、喉部の黒い大きな斑がありません。キセキレイは留鳥ですから冬も春も見られます。ハクセキレイの一部のものは渡りをしますし、夏と冬で体色を変化させますが、ハクセキレイは年中同じ体色で通
します。日本全国の河川周りに生息し、セキレイの仲間では一番標高の高いところにまで生息します。 |
||
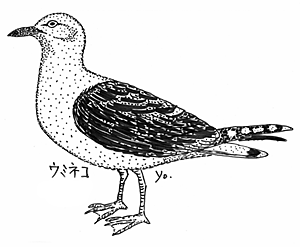
|
青い空 ウミネコがいて 夏祭り 虚心
|
||
|
私の夏休み。東北地方に2500kmの旅をしてきました。青森市が旅の北端で、縄文の都と地元の人々が語る三内丸山遺跡を見物。ねぶた祭りでは若いアネコに手を引かれて、ねぶた衣装で跳ねておりました。 この旅でよく見た鳥はセキレイの仲間です。河原に長くいたからです。キセキレイ、ハクセキレイなどですが、セグロセキレイは見ることができませんでした。カッコウが川を横切るのを見たときは感動を覚えました。
|
||

|
高原の 涼風揺らす ホシガラス 虚心
|
||
|
2001年の夏はやりきれない暑さが続いています。夏の暑い日が続くと思い出すことがあるのです。 この日は山の温泉に入って筋肉をほぐし、ビールを手にして中央線の旅人になったのです。しかし、暑い東京に帰ってきたら、すぐさま高原の住民になりたいと強烈に思うのでした。ホシガラスを見たのはその一回限りです。思い出を強烈に残しておくためには、以後その姿を見なくていいと思っているのです。そういう思い出の野鳥はホシガラスだけです。 |
||

|
カワガラス 直っすぐに飛ぶ 渓の夏 虚心
|
||
渓流を棲みかにする野鳥ではカワセミが有名ですが、私はカワガラスが好きです。スズメよりもうんと小さなミソサザイは日本で一番小さな野鳥です。カワガラスはスズメよりずっと大きく、ムクドリに近い大きさです。ミソサザイは渓流の茂みに隠れながら、また尾羽をピョンピョンとせわしく動かして行動しますが、カワガラスはいたって鷹揚で、河原の石から木陰や別
の石に長い距離を直線的に飛行します。飛んでいった先を目で追えば次の行動を続けて観察できます。逃げも隠れもしませんよ、といった雰囲気がいいですね。カワガラスは雄雌同色です。 |
||

|
山百合の 清さにうたれて コゲラ啼き 虚心
|
||
| 山百合の花が盛んです。住まいのある神奈川県相模湖町が定めた町の花が山百合なのですが、山影の土手の山百合の茎が道に向かって伸びたと思ったら、大きな白い花が咲き出しました。山百合の花は単純に白いのではありません。花びらのなかほどに黄色い縞がとおり、そのあたりに赤い粒が転々と刺しています。山百合の花は、この黄色と赤い転々が味わいでもあります。カサブランカの白いだけ、大きなだけというのは人工的にみえて面
白くありません。 その白い山百合を見ながら、この花に似合う野鳥はなんだろうとこの2週間考えておりました。山百合と一緒にすると味わいの出る夏の野鳥となるとこれが難しいのです。 そんなことを考えている間にヒグラシが鳴き出しました。最初に聞いたのは7月1日ですが、裏山の杉の木立から声がしたのは7月15日でした。そのとき一緒に声を出したのがコゲラです。低いジュジュという声です。 コゲラは遠慮がちに啼き、クルミの木をコツンコツントつついています。地味な姿で派手な行動をしないのがコゲラです。姿も白と黒の縞模様でオスは目の後方にわずかに朱をいれています。白と黒の間には茶が混じりますが印象には残りません。スズメよりわずかに小さいかな、というサイズで家の周りにも姿を見せるのです。 コゲラは留鳥ですから秋にも冬にも春にもいます。郊外の民家の近くにも生息する野鳥ですから目撃することが多いものです。 |
||
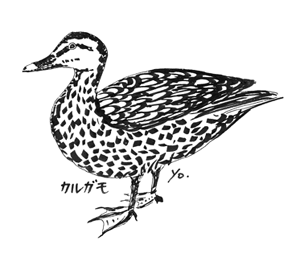
|
オニヤンマ カルガモのそば すいと飛ぶ 虚心
|
||
日本の夏に居残っているカモがカルガモです。というよりもカルガモは留鳥です。家の近くには相模湖と津久井湖があり、ここに幾筋もの沢が流れ込んでいます。5月過ぎにヤマメを見た阿津川にカルガモのつがいが姿を見せていました。 |
||

|
アカハラが キョロンキョロンと 夏盛る 虚心
|
||
この夏はアカハラが裏の林でよく啼きます。家の前の電線にまで足を伸ばしてきます。春から夏にかけてウグイスとアカハラが歌声を競っています。アカハラのキョロン・キョロン・チィーにウグイスは負けたくないようです。今年のアカハラのはしゃぎ様は何が何でも人の気を引きたいものと思えたので、写
真を撮ってやりました。400の望遠レンズで十分に足りました。 |
||

|
コロコロと 夏至の朝告ぐ ゴジュウカラ 虚心
|
||
夏山登山で八ヶ岳にはよく通いました。赤岳鉱泉のテント場まで標高をかせぐと翌日の行動がうんと楽になります。
ゴジュウカラとの出会いはここでの野営のときでした。ゴジュウカラの啼き声は、私の耳には「コロコロ」と聞こえるのです。これはとても鳥の声とは思えません。6月の夏至のころに八ヶ岳に出かけたときのことでした。「コロコロ」という啼き声は、コオロギにして時期が早いしおかしいなと思いました。夜も明けきらないうちから「コロコロ」と耳に騒がしいのです。この啼き声は「チッチッチッ」と聞こえる人もあるそうです。これは地啼きで、さえずりは「フィーフィーフィー」なのだといいますが、私の耳には「コロコロ」に「チッチッチッ」を混ぜたような啼き声しか聞こえません。この不思議な声がまたかしましいので、テントの中から覗いていましたら、木の幹を頭を下にして歩きながら「コロコロ」と啼いている鳥がいるのです。これがゴジュウカラでした。 八ヶ岳の行者小屋付近は、赤岳鉱泉とは離れておりますが、こちらは白骨樹が林立して異様な風景です。赤岳鉱泉を起点にして、硫黄岳に向かうと夏至のころにはまだ雪が残っています。その雪が消えた石ころだれけの平らな場所にはコマクサが桃色の花をつけています。そしてさらに進んで赤岳山方面 に向かう岩場には、人を怖れないイワヒバリが「ピョピョピョ」と啼きながら姿をみせてくれます。赤岳付近はイワヒバリが多いのです。雷鳥は八ヶ岳ではみることができません。ヨーロッパアルプスでもイワヒバリをみますが、日本のイワヒバリの方が可憐ですからで私は好きですね。雀もヨーロッパのものより日本のものがいいですよ。 八ヶ岳に出かけますとゴジュウカラ、白骨樹、コマクサ、イワヒバリと衝撃だらけです。下山ルートを清里方面 にとりますと、夏至のころには途中の美しの森のレンゲツツジは見事ですし、聖泉寮に立ち寄りますと軒下にイワツバメが巣を掛けています。清泉寮は今は混み合いすぎておりますが、いいところです。 夏はいいですね。昼が長いことなどもあって私は大好きです。 |
||

|
アジサシの ひらり舞う夏 鮎はねて 虚心
|
||
6月1日、多くの川では鮎が解禁になります。鮎師たちのなかにはまちこがれるあまり川で夜を明かす者もいます。私は自宅近くの相模川の様子を解禁前から観察していましたが、いつもはみえる鮎の姿がないのです。当日は相模川の要所をみてまわり、釣れていないことが確認できましたから、酒匂川に足をのばしました。竿を出したのは日が高くのぼってからのことです。酒匂川は相模川より水の綺麗さがづっと上ですから、鮎の味もいいのです。川につかっていますと岸辺の葦のなかから、オオヨシキリのキッキッキッあるいはギョギョギョという激しい鳴き声が聞こえてきました。オオヨシキリは河原のカシマシ屋さんという趣です。それでもオオヨシキリの声は、河原に活気を呼び起こす夏の風物詩です。 オオヨシキリの鳴いてる夏はいいなあと思っていましたら、竿の上をアジサシの仲間がゆっくり舞っていて、それがいかにも優雅なのです。シロアジサシでした。コアジサシやアジサシには羽根には灰色が混じっていますし、目や頭の一部は黒いのですが、このアジサシにはそれがありません。どこも真っ白で優雅に飛ぶ鳥はシロアジサシでした。シロアジサシは熱帯地方の海域に棲んでいて、日本では迷鳥として取り扱っている野鳥です。 迷鳥をみるのはさほどうれしいものではありません。一羽や数羽では仲間が少なすぎてさみしいだろうと思えるからです。 |
||

|
ホトトギス ひねもす啼いて 夏が来る 虚心
|
||
このところしきりに裏の林でホトトギスが啼きます。
|
||

|
カワセミと 自然の恵み 交歓す 虚心
|
||
| カワセミは清流を象徴する野鳥ですから、カワセミは自然の象徴にもなってしまいます。東京神田の駿河台下の交差点にある書泉グランデのビル屋上の大看板にはカワセミが描かれています。三省堂が近くにあり、古書街の天空に翡翠(ヒスイ)と青を身にまとった極色彩
のカワセミがいるのです。現代人の自然観をどんな形かで現しているとみます。 夏の休日には私は鮎釣りのため川で過ごしております。相模川支流の中津川や道志川でカワセミをよくみかけます。中津川は宮が瀬湖を水源にするようになりましたが、愛川町を下って厚木市で相模川に合流します。道から隔たった愛川町の河川にもカワセミは棲息しています。ススキジムニーが優勝者に贈られる鮎の友釣り大会が開かれたここでは、竿をだしている流れの頭上の枝にカワセミが陣をはっていて、ピョコン、ピョコンと飛び込んでは小魚を捕らえていました。 のどかだなその景色にしばしの間、仕合わせを感じておりました。大会での釣果 は私のホームページの鮎釣りの欄に掲載しておりますが、ジムニーははるか彼方の存在でした。 野鳥とつきあうとき、野鳥を遮二無二見に行くというよりも、自然との遊びのなかで出会うという方が人の側に余裕があっていいですね。 鮎釣りをする道志川の此の間沢キャンプ場の下流の奥相模ダムへの流れこみの崖にもカワセミは営巣しています。監視員さんは人のこみあわない場所で、検札の合間に鮎を釣っているのですが、あるときはこの場所でほくそ笑んでいました。その年、その季節に釣れる場所を知っている監視員さんの行動は釣り場センサーでもあります。 せせらぎの音だけが聞こえる自然のなかでカワセミと遊ぶのは贅沢というものかも知れません。 |
||

|
漁り火に 幽玄の影 鵜飼漁 虚心
|
||
上野の不忍池にたむろするのはカワウで、ここはカワウの集団繁殖地になっています。
|
||

|
青空は ヒバリの声で 澄み渡り 虚心
|
||
| 春も深まって山の緑が新緑から深緑色に移り変わるころに天空で、ピィーチク・パァーチクにぎやかに歌うのがヒバリです。山は落葉樹の新緑と杉や松などの常緑樹とが分離して見えるので立体感がうんと増します。半袖になりたいほどに陽気のいい晴れた日にはヒバリがよく似合います。ヒバリの声は初夏を楽しんでいるようです。 家の周りの麦畑や桑畑の上空でヒバリがよく歌います。上空に舞い上がったヒバリは羽根を半開きにして小刻みに振るわせて静止して歌います。上空で歌うのは雄で、雌は畑に潜んでいるのです。餌は昆虫などです。ヒバリほど春を文句無しに象徴する野鳥はいないでしょうね。 ヒバリを探しに野を歩いているときトンボを3種ほど見かけました。一つは川トンボのようなやつ、もう一つはギンヤンマを小型にしたようなやつ、さらにもっと小型のやつです。4月末から5月始めにかけてのことです。 野を歩きながらついつい川を覗いてしまいます。家の近くの道志川まで足をのばしますとそこは立派な渓流です。すぐ近くを相模川支流の阿津川が流れていますが、5月になりましたら魚影が見えました。群れて泳いでいるのはアブラハヤでしたが、その横にヤマメがいました。20 ほどもある肥えたヤマメです。散歩のとき3度ほどその姿を見ましたが、連休後半に3日ほど家を空けていましたらヤマメは姿を消しました。阿津川は生活排水が流れ込むのでさほどきれいな川ではありませんが、それでもヤマメが棲んでいるのです。釣ってきたヤマメを放流しておこうかなと密かに考えていた川ですから、私はヤマメを見て小躍りする思いでした。 |
||
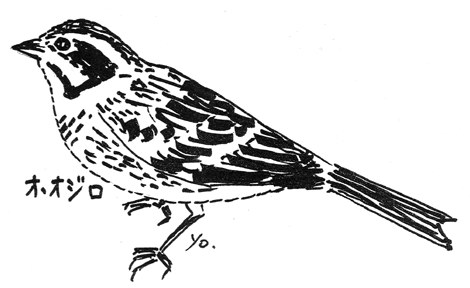
|
ホオジロが さえずり交わす 陽の温(ぬ
く)さ 虚心
|
||
| ホオジロは里山の代表的な野鳥です。人の近づくのを察して藪陰からチチッと鳴いて飛び出します。比較的長い尾羽の両端にある白い帯が目立ちます。この尾羽の白がホオジロの象徴だと思います。頬の白さからその名前がありますが、これは捕まえたホオジロ間近に見て命名したものだと推察します。 山にも人里にもいる野鳥のなかで人に媚びないで粛々(しゅくしゅく)と生きているのがホオジロです。その生き方に人間は学ぶものがあると思っています。春にも、夏にも、秋にも冬にもホオジロは人里で暮らしております。チチッ、チチッという鳴き声ですぐホオジロと分かります。野鳥を知らない人はホオジロと似たカシラダカとの区別 がつきません。雀とカラスしか判別できない人は多いのです。 ホオジロは雀より少し大きく、姿は均整がとれていて私の一番好きな野鳥です。雄と雌では頬の白い模様が違い、何といっても雄の姿がいいですね。ケバクなく地味でなくその渋さといったらありません。チチッ、チチッというのが地鳴きですが、春になると新緑のてっぺんでくつろいだ姿でピチュピチュとさえずります。縄張りを主張しているのでしょうか、別 な野鳥が近づきますと一瞬身構えします。もう、春もたけなわです。タケノコを掘る時期でもあります。 4月1日、犬を散歩のお供に裏の畑の小道を歩いておりましたら、ツバメの飛翔するのを見ました。目の錯覚かなとも思いましたが、4月3日に相模湖駅の軒下にツバメが来ているのを確認しました。それから日が過ぎて今日は4月17日です。ツバメは産卵行動に入っておりますし、雀などは一番雛が孵りました。他の野鳥も産卵を始めています。 野に出てホオジロをみると私は安心します。ここには自然があるのだと。とは言いましてもホオジロが棲みやすい環境条件は落葉低木や芦原があることですので、この環境条件が無条件にいいということはできません。それでも都会にはホオジロは居ません。 それでは春の野をを代表する鳥はなんでしょうか。ヒバリだと思います。私はこの鳥を今年はまだ見ていないのです。 |
||
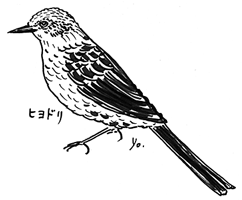
| ヒヨドリが 花見の宴に おおはしゃぎ 虚心 | ||
| ヒヨドリは桜の花が満開になると花をついばんでビャービャーとおおはしゃぎです。春の里山で目立つ野鳥はヒヨドリ、ホオジロなどですが、ずうずうしさにかけてはヒヨドリという野鳥の右にでるものはないでしょう。あえていえばハシブトガラスとカワラバトかな。ムクドリもヒヨドリに迫りますが身体が少し小さいのと道化た姿ですからヒヨドリには及びません。 私の住む里山の桜は4月8日に満開でした。カメラを担いで津久井湖や相模川、道志川などを散策に出かけたのですが、ヒヨドリは5月下旬のポカポカ陽気に浮かれてビャービャーと満開の桜の枝を飛び回っていました。ヒヨドリの声は大きいので、桜にきている他の野鳥がかすんでしまいます。 道志川にも相模川にもカワセミがいます。道志川は相模川の支流ですが、枝分かれした上流部といった方が実体をよく表しています。道志川の上流部から津久井湖に注ぐ下流部までカワセミは生息しています。この日は道志川の満開の桜の木の下から1000 の望遠レンズをカメラに付けたバードウオッチャーに出合いました。カワセミの定点観測をしている人ですが、クロカン四駆で河原に乗り入れて川遊びしているグループがいるためカワセミが姿を見せてくれないのだそうです。カワセミは夏が似合う野鳥ですがこの日、日中は半袖で用が足りるほどに気温が上昇しました。カワセミのことは別
の機会にふれたいと思います。 |
||
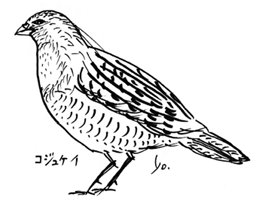
|
コジュケイの 二羽いた跡に ハコベ萌え 虚心
|
||
| コジュケイは足下から急に飛び出します。ときどきは道路に出ている姿をみますが、落ち着いて観察したことがありません。朝一番に飼い犬の糞尿を済ませるため立ち寄る林で、コジュケイがよく餌をついばんでいます。ここは、うらなりの野菜は収穫しても面
白くないので、次の苗を植えるときに根ごと引き抜いて捨ててしまう場所なのです。春先の餌の乏しいときにはコジュケイの格好の餌場になるのでしょう。 ツガイのコジュケイがここで私と飼い犬を毎朝迎えてくれるのです。ウヅラより一周りほど大きく、キジバトほどの身体をしたコジュケイは愛嬌者といえます。道路に出ていて人の前を何メートルも一緒に前進するときなど、タモ網で捕まえられるかなと思うこともあります。鳴き声は「チョトこい、チョットこい」というものなのだそうですが、私はコイジュケイの鳴いている姿をみたことがないのです。 コジュケイは日本にもともといた野鳥ではありません。中国が原産ですが大正年代に飼鳥が逃げて野生化したということであり、その後は猟のために積極的に放鳥したのが居着いて、日本の在来種のような顔をするようになりました。ウヅラよりは華やぎのある体色であるものの度ぎつさはないので日本の野にいても違和感はありません。 この春のウグイスの初鳴きは3月21日でした。鳴き出すと遠慮がないのがウグイスです。毎日毎日、ホーホケキョの声が聞こえます。紋白蝶は3月22日に見ました。関東地方は春分の日を境に確実に暖かくなります。東京地方の桜の開花宣言は3月23日に出されました。暖かくなると縮こまっていた心も身体もノビをしなければなりませんが、人は必ずしも春だからといって心が浮きたつものではないようです。日照時間の延長が心模様に影響して気だるくなる人が少なくありません。狼はどうしたわけか満月の日に異常に興奮するのです。現在の科学の力は万能ではありません。観察を通 じて法則のようなものを見つけだしはしますが、その訳を説明をできないでいることが多いのです。 動物たちは季節が冬から春に動くのにあわせて生命の活動を輝かせますが、人間の心は労働を通 じて年中均一であるように訓練されてきました。春や夏や季節の到来にあわせて浮かれ出すことはありませんが、祭りで浮かれてそれを調整してきたともいえるでしょう。 自然のなかで野鳥を観察するということは祭りのような個人の行事ですが、それをしているからといって必ずしも心が晴れているということではありません。お天道様にも照る日曇る日があるように、心に雲がかかる日も少なくないのです。 晴れたらいいね、と思っても心の曇る日には無理をしないのです。曇る日は、一日とゆっくりと自分の心と向き合うのも人生を過ごすための方便であるように思われます。 |
||

|
春の日を 黄金に透かす カワラヒワ 虚心
|
||
| 冬から春への季節の移行は日差しの変化として感じとることができます。眩しさを増した春の日差しによく似合うのがカワラヒワです。上空を飛翔するカワラヒワの風切り羽根は黄色の横一文字が鮮やかです。カワラヒワは高い梢で翼を震わせてコロコロと鳴きときどきジュイーンの音をいれます。このジュイーンという鳴き声はマヒワに良く似ています。カワラヒワはまた翼の肩部分と尾羽の元の部分の黄斑が目立ちますし、それとあわせて黄緑の体色であることから彩
りの冴えた野鳥です。コロコロという独特の鳴き声と彩り豊かな姿であるため野原でよく目立ちます。カワラヒワは雌雄同色ですが、さえずりなど鳴き声で見分けます。 カワラヒワは留鳥であり、河原の名を冠されていますが、野原や低山で生活しており、人をあまり恐れない陽気な野鳥です。ですから四季を通 じて里山で間近に見ることができます。 3月18日朝、散歩をしておりましたら一羽のカワラヒワが道端の草むらで死んでおりました。春が随分とすすんできて、これから賑やかに繁殖の時期を迎えるというのに可哀相です。元気に飛びかっている野鳥はどのように死を迎えるのでしょうか。小鳥は一般 に食い貯めが効きませんので一日中餌を探して飛び回ります。少し体力が低下しますと生きていけません。草むらのカワラヒワは綺麗な羽根をしておりました。鷹などに襲われた痕跡はありません。私はそのカワラヒワをスケッチして葬りました。 長野県小布施町の豪商高井鴻山の記念館を訪ねたときに葛飾北斎の野鳥のスケッチを見ました。スケッチには死んだ鳥もありました。遠くの動いている鳥はすみずみまで観察しにくいものです。絵師は仕事をするのにモノをよく観察するということとして私は理解しました。 梅の花が咲き誇る野辺の高い梢で翼を震わせてコロコロ、ジュイーンと鳴くカワラヒワは、春を梅から桜へとつなぐ使者だと思いました。 |
||
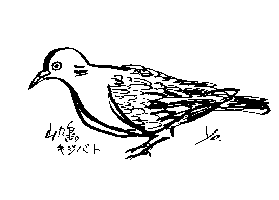
|
畝(うね)起こす野辺で見合いの春の鳩 虚心
|
||
| 3月12日朝、耕運機を入れた畑に10羽ほどの山鳩が群れていました。この日、住まいのある相模湖町では雪がちらつきました。通
勤電車が新宿駅を通過する頃、乗客の「雪だ」と話す少し興奮した声が耳に届きました。 鶯(うぐいす)の初鳴きは未だです。3月15日に聞いた年もあるのですが今年はどうでしょうか。この冬はよく雪が降りました。家の周囲の日陰には1月末の28センチ(メートル)もの降雪のなごりがあります。山鳩がペアを組むのはもう少し先なのでしょう。これが群れている山鳩の今シーズンの見納めになるのかな。うららかな春の野辺の山鳩の鳴き声に思いがとびます。また、むせ返る緑の山中の山鳩の姿が目に浮かびます。夏が恋しいのです。昨年の夏の暑さをもう忘れて、夏が恋しくなっているのです。 山鳩はキジバトともいいます。山鳩の鳴き声はどんなでしょうか。日本人の耳には「デデポッポ」と聞こえるのです。幼児には「ポッポッポ(鳩)ポッポ」と聞こえるようです。 梅の花は今が盛りです。沈丁花もいい匂いを放ち始めました。1週間もすると桜前線のニュースがテレビでかしましくなるでしょう。この時期は冬鳥との別 れの時でもあります。冬鳥は人の近づくのをはやくから知っていて、間近になるとヤブの中に姿を隠します。凍てつく季節を慰めてくれた冬鳥たちに「ありがとう」の言葉を贈りたいのです。もちろん留鳥たちは人里にうんと近寄ってきて十分にいやしてくれていますが、やはり渡りを控えた冬鳥たちに感謝をしたいのです。 私たちの小さな畑に前日、馬鈴薯を植えました。ポカポカ陽気に妻が浮かれてしまったのです。 日本野鳥の会が高尾山で探鳥会をしますとドバトが一番に多い鳥としてカウントされます。ハシブトガラスが三位 です。山鳩(キジバト)は十位です。季節によりこの間に様々な野鳥が出入りしますが、ヒヨドリ、メジロ、スズメのほか、カラの仲間が常時名を連ねます。ドバトが山に進出して、山の鳥だったはずの山鳩が里山からさらに都市部に降りてきています。山で探鳥をしてドバトを見なければならないのは、人生が意に反したことばかりであるのと重ね合わせて考えれます。 日本中にまんえんしたドバト(カワラバト、伝書鳩のこと)は糞害をもたらすので閉口します。山鳩は畑に植えた種子を幾分かほじくるとはいいましても、それに増して小鳥たちは病害虫を駆除してくれますからみな畑の守り神です。山鳩がいる風景はのどかさの証明みたいなものですから、それだけでも十分に役目を果 たしているといえるでしょう。この山鳩も空気銃の規制がなされるまでは種の存亡の危機に瀕したこともあるのです。アメリカでは旅行鳩が狩猟によって絶滅してしまったのです。 のどかさや山里を象徴するものとして山鳩が日本の歌謡曲に歌い込まれています。山鳩を歌詞に折り込んだヒット曲を探してください。 |
||
|
鶯の初鳴き聞いて春が来る 虚心
|
||
| 三月十五日の日曜日の朝、風呂に浸かっていると「ホーホケキョ」とウグイスの声。一九九八年の初鳴きでした。といっても私は木、金、土と家を空けていたのでこの三日間のことは知りません。 この日ウグイスは「ホーホケキョ」と明瞭に五回ほど鳴いて静まりました。翌朝は朝五時四十五分に家を出て、水曜日まで帰りませんからウグイスのことは分かりません。 ウグイスの初鳴きの日は山梨県の渓流が解禁になる日でした。所用があって家を空けられませんでした。出かければ三十センチの岩魚は間違いなし、山女魚も三十センチを超えるものが釣れる場所があるので、雑事が恨まれます。 ウグイスには二つの大きな思い出があります。 一つは鮎の解禁日の六月一日のことです。茨城県の御前山町を流れる那珂川でのこと。腰近くまで立ち込んでの大河の釣りでした。岸の向こうの小山で一日中ウグイスが鳴いていました。親しくなった釣り人が「この長閑(のどか)さがいいんですよ」と話していました。もう山は緑濃いものの、真夏に少し見える河原のやつれがないのが六月の解禁日です。 もう一つの思い出は真夏の上高地の散策路で鳴くウグイスのことです。 このウグイスは人通りの小枝に姿を丸出しにして「ホーホケキョ」と踏ん張っていました。手を伸ばせが捕まえられるほどの所です。づうーっと鳴いていました。 上高地の小川の流れには岩魚がいっぱい泳いでいます。捕って食われないと知ると鳥も魚も人を恐れなくなるのです。 東京近郷のウグイスの初鳴きがいつ頃であるか私は知りません。東京近郷という抽象的な表現では人を惑わしますから、私の住まいの在処(ありか)を述べます。神奈川県津久井郡相模湖町若柳六四一−六です。JR中央線で八王子駅、西八王子駅、高尾駅につづく相模湖駅が最寄り駅です。住まいは東京の野鳥の宝庫である高尾山の山稜が張り出した所にありますから、裏山は高尾山ということになります。住まいの向こうの林のさきは湖の末端です。ウグイスが好む藪(やぶ)があります。 |
||
|
つばくらめ桜見たさに舞い戻り 虚心
|
||
| 春告鳥は沢山ありますが、ツバメもそうした鳥の一つでしょうか。 相模湖も東京も今年は四月四日の土曜日には桜の花は満開になりました。相模湖の桜は町の観光協会が宣伝している「名物」です。その桜の花を撮ろうとカメラを担いで相模湖駅に出かけたらツバメが駅舎の周りを飛んでいました。街中の古い商家の開けっ放しの店先にも一組のつがいがいました。梁に掛けられた巣は去年のものでした。今年の巣はこれから造るのでしょう。 「ツバメが来る家は幸福な家だ」といいます。私の家にはいまだかつてツバメが巣を掛けたことはありません。 日曜日に夕暮れの裏山を眺めていたらツバメが飛ぶのを目撃しました。夜遅くまで雨戸を締めずにいたら蛾が窓ガラスに来て羽根を震わせていました。昼に窓を開けたまま外出したら虫が家に入っていました。モンシロチョウの飛ぶのも見ました。ツバメが活動する季節になったのでしょう。そういえば普段はビャービャーと騒がしいヒヨドリがまだまる裸の栗の木にとまって一日中ピィーチョロリチョロリと歌っていました。 |
||
|
鷽(うそ)鳥も桜の開花に小躍りし 虚心
|
||
| 「咲いた咲いた桜の花が咲いた」と思ったらもう新緑の季節に移り、ツツジやサツキの季節になりました。といっても北海道や青森はまだ少し先になります。 桜が咲くとそれまでの枯れ野原が一気に活気付きます。野の鳥のさえずりの声が一段と高まり、冬鳥が場所を明け渡すのです。 裏藪のウグイスは朝、昼、晩を問わず遠慮なしにホーホケキョを連呼するようになりました。 ヒバリはウグイスの向こうを張り、天空でピイチクパーチクよく歌います。 春が来ると特別に嬉しくなるのは野の暮らしをしている人と雪国や北国の人々です。 さて桜の花のことです。桜の花を啄む小鳥は多いのですが、私のウソの記憶は桜の花とともにあるのです。ウソはアトリ科の鳥でヒー、フーと鳴きながらずうずうしい位に桜の花を啄みます。見ていてもったいないと思いますが、桜の花がこの世からなくならないことを考えますと害がないのでしょう。 山桜が楚々と山肌に色を添えるようになりました。 |
||
|
雉鳥が鎧を誇る春の野辺 虚心
|
||
| キジは日本の国鳥に指定されている。どこかの県の県鳥でもある。この鳥はヤマドリ等とともに狩猟の対象にされている。猪狩りなどは勇壮だが鳥を対象とした狩猟は少し趣を異にする。ハンターが打ってきたキジを間近に見てその羽根の美しさに驚愕したものである。 春の野辺で「ケンケン」という鳥の声がするので、振り向くとキジの姿があった。周辺を二輪車を使って散策するとキジの声が幾つも聞こえてきた。高尾山の南稜が伸びる相模湖のこの界隈にはキジが相当数生息していることが分かった。 「それほどに自然が豊かなのだろうか」と気持ち引っ掛かるものがあったのだが、この原因が判明した。隣接の畑の所有者の七十五歳になる榎本さんとキジのことを話していたら相模湖ピクニックランドで飼育していた二十つがいほどのキジを放したのがそのまま野生化して繁殖しているのだという。もっともキジは自然といっても人が農耕生活を営む山里に主として生息するのであるから何処にいても何の不思議もないものである。 春になるとキジの活動が活発になって、裏の空き地に終日出没して、不意に足元から飛び立って驚かせる。ケンケンという声は雄が発するものである。声のするあたりの何処かに必ず雌がいる。雌は地味な姿である。 さきほどの榎本さんの話の続きである。栗林の下草を除草機でバリバリと刈っているとバッシィという音とともにキジを刈ることがあるのだという。抱卵したキジは除草機の迫るのにもたじろがずに巣を守るのだという。いまキジは巣作りに入っている。 つがいで行動しているキジの雄は遠くでケンケンと声がするとそれに応えるように胸を反らしてケンケンと鳴く。その意味するものは何であろうか。「キジも鳴かずば撃たれまい」なのであるが、「キジは鳴かずにいられない」のであろうと推察する。 |
||